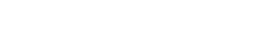1. アトピーは治るのか
「アトピー性皮膚炎は治るのか?」
アトピーに悩む患者さんとご家族にとって、最も大きな意味を持つこの問いに、わたしはこう答えます。
「はい。治る病気です」と
わたしは漢方相談を仕事にして30年が経とうとしています。2007年に国際中医主治医師(中医専門員2A )を取得し、2011年からは漢方相談を専業としてやってきました。2011年以降、病院で治らない皮膚のお悩みの方のお力になりたくて、中国雲南省の大学病院(雲南中医皮膚科医院)、広州の広州中医薬大付属病院など複数の大学病院の研修で得た「中医皮膚科」の治療法に基づいた漢方相談を行っています。
健康相談を30年行ってきて、ご相談をお受けした人数はもう数えきれませんが、延べ2万人は下らないでしょう。とくに漢方相談を専業にしてからはアトピー性皮膚炎のご相談も多く、500人以上の方の改善に立ち会ってきました。完全にアトピー性皮膚炎が治って漢方相談を終了(ご卒業)していかれた方も少しずつ増えてきました。
その経験から、「アトピー性皮膚炎は治る」と確信を持って言うことができます。
では、その理由をご説明していきます。
2. アトピーとはどんな病気か<原因・発症・症状・悪化・再発>
・アトピーの原因
西洋医学的にいうと、アトピー性皮膚炎の原因は2つです。ひとつは「アレルギー」の問題、もうひとつは「皮膚のバリアの脆弱さ」です。順にご説明します。
○アトピー性皮膚炎を起こす「体質」
アトピー性皮膚炎は、皮膚で何らかのアレルギーが起こり、そのせいで炎症が起こってプツプツ(丘疹)や赤み(紅斑)、腫れが起こりとても痒いです。アレルギーの起こりやすさは、過労やストレス、食事の乱れなどの後天的な影響もありますが、もともとの「体質」、つまり先天的な、両親から受け継いだ遺伝子に由来する部分もあります。*¹
人体にとって異物(自分以外のモノ)が体内に侵入した場合、免疫がその異物の排除に働きます(免疫応答)が、そのときに過剰な反応を示してしまうことがあり、本来は不必要な炎症が起こってしまうことがあります。この過剰な反応による不必要な炎症がアレルギーの正体です。
皮膚でのアレルギーが原因で起こる不調にはいくつかありますが、繰り返し続くアレルギーでなかなか終熄しないのがアトピー性皮膚炎の特徴と言えます。
○皮膚のバリアの脆弱さ
皮膚は外界と接する臓器で、外界のいろんな物質や影響から身を守る働きをしています。と同時に、汗や皮脂を作って皮膚表面に放出したり(分泌)、常に隙間なく新しい細胞を生み出して外へ外へと押し出していくと同時に、皮膚表面の細胞の隙間を「うるおい」で満たしたり、最後は垢となって剥がれていく新陳代謝を行ったりしています。
アトピー性皮膚炎を発症しているひとの何割かは、細胞を隙間なくぴっちりと埋め、細胞の中で「うるおい」の元を作る働きが遺伝的に弱いことが発見されています。*²
アトピー性皮膚炎の原因には、この「アレルギーを起こしやすい」体質と、「皮膚のバリアが脆弱」な体質との2つの要素があると言われています。
・アトピーの発症
では、実際にアトピー性皮膚炎を発症するのはどんなときか。アトピー性皮膚炎の発症がよく見られる時期は「乳児期」と「幼少期」 です。
まず乳児期です。生後3ヶ月頃まで赤ちゃんの体内では男性ホルモン(アンドロゲン)が増加する影響で皮脂の分泌が盛んになります。過剰な皮脂に皮膚の常在菌が作用すると皮膚へ刺激になる物質が作られ、その刺激で乳児湿疹(乳児脂漏性皮膚炎)が起こると言われています。*³乳児湿疹の多くは時期がくれば落ち着くと言われますが、慢性的に湿疹が出続けてアトピー性皮膚炎へと発展する場合も多いです。
次に幼少期です。小さな頃は皮膚が乾燥しやすくバリアがまだ弱いです。そこへ何らかのアレルギーによる炎症が起こると長引きやすくアトピー性皮膚炎を発症します。昔「成長とともに治る」と言われていたこともありますが、現代では症状が続く方も多く、そのまま成人アトピーへ進む場合も少なくありません。
乳児期や幼少期ほど高率ではありませんが、大きくなってから突然発症する方もいます。学業や仕事に伴うストレスや過労、睡眠不足などによる免疫低下に、外食やファストフード、お菓子などを多く摂取する生活習慣が重なり、ついにアレルギーによる炎症が起こって止まらなくなり・・・というお話をよくうかがいます。実際に思春期以降に発症する方が近年とても増えています。
成長とともに治まっていたアトピー性皮膚炎の再発が見られることもあります。更年期などはお肌が弱くなって肌トラブルが多く見られますが、アトピー性皮膚炎もこの頃合いに再発し、思うように改善しないケースがよくあるので要注意です。
・アトピーの症状*⁴
乳幼児期では、頭部や顔面に「赤み(紅斑)」が現れ、「カサカサと皮膚がめくれてくる(鱗屑)」、「湿疹(丘疹、とくに引っ掻くと汁が出る)」が見られ、次第に身体へと広がっていきます。ジュクジュクと汁っぽくなる(滲出液)傾向があります。口の周りや顎に、付着したよだれや食べものの刺激で赤みや湿疹が出ることもあります。
体幹や腕・脚は乾燥してトリハダのようにザラザラしがちだったりもします。
小児期では、皮膚全体が乾燥してツヤやふっくらした柔らかさを失いがちです。肘や膝の内側や腋などに引っ掻き傷ができ、繰り返し掻き壊すことで徐々に皮膚が硬くなってゴワゴワ(苔癬化)してきます。耳切れしたり、体幹の乾燥から湿疹を発症することもあります。
思春期・成人期では、小児期の症状がそのまま残りつつ、長い年月掻き続けたことでゴワゴワ(苔癬化)部分がさらに広がり、上半身を中心に広く色素沈着、ザラザラとキメが荒い乾燥した皮膚状態、いわゆる「アトピー皮膚」になってきます。繰り返す掻き壊しで眉毛も外側から薄くなったり、顔の赤みが目立ったり、首からデコルテ辺りに細かい茶~グレーの横じま(「さざなみ用色素沈着」)ができてしまうこともあります。力を入れて掻いてしまいがちな腕・脚には虫刺されのようなサイズ・見た目のポツポツ(痒疹)ができて、繰り返すことも。
・どんなときに悪化するか
アレルギー反応がきっかけの場合、悪化するのは「アレルギー反応を引き起こす物質(アレルゲン)に触れたとき」です。
化粧品や洗剤、食品などの物質に触れたことがきっかけでアレルギー反応が起こって悪化することもありますし、花粉や排気ガスなど空中を漂うものに反応することもあります。
バリア機能が脆弱な体質の方は、冬、体温を逃がさないよう皮膚の下の血管が収縮し、皮膚を守るバリアの材料が届きにくくなる寒い時期に悪化しやすい性質があります。
また、暑くなって、湿度も高い夏季の再発も多いです。こちらの理由については後述します。
・患者さんを悩ませる「再発」
アトピー性皮膚炎は「波」がある病気と言われます。
皮膚のバリアの脆弱さや免疫状態が基礎にある病気ですので、何かのきっかけがあれば炎症が再燃し、「再発」します。
皮膚のバリアや免疫状態は生まれ持った体質で、「変えられない」ものだとされているので、再発を防ぐためコンディションがよい時期でも塗り薬を少量塗り続ける方法が試されたりしています。
3. アトピーと医療<治療法の効果と実態>
・西洋医学/現代医学による治療法の効果
先にお伝えした通り、アトピー性皮膚炎は体質の影響が大きい病気です。
そこで、皮膚科など病院では、薬を用いて、湿疹など症状をコントロールすることを目的とします。具体的には、炎症を鎮めるステロイドやタクロリムス(プロトピックなど)といった塗り薬を適宜塗り、痒みが辛いときには掻き壊しによる一層の悪化を防ぐため痒みを和らげる薬を飲みます。症状に対してステロイドを塗るといった従来の方法だけでなく、再発予防のためステロイドを長く広く塗っていく治療法が選択される場合もあります。
また、皮膚で起こる過剰な免疫反応の仕組みが解明されるにつれ、その過剰な反応を抑える効果を持つ新しい薬も登場し、ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害薬(「コレクチム」)、PDE-4阻害薬(「モイゼルト」)、抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体(「デュピクセント」)といった塗り薬・注射剤など、治療法の幅も広がってきました。
症状の出ている場所や症状の強さに応じて、それぞれに適合した薬剤を選べるようになっており、症状のコントロールは以前に比べてしやすくなっていると言えます。
・西洋医学/現代医学による治療法の実態
ただどの方法も、出てきた症状をいかに抑えるかに主眼が置かれています。
西洋医学/現代医学では、第2章で見た通り「アトピー性皮膚炎は体質の病気である」=「治らない」という理解なので、「治らない以上、よりよくコントロールする」がゴールとなるからです。
つまり、「そもそも炎症が起こらない体内の状態」を作っていく、「バリアや免疫のコンディション」を整えて再発を防ぐといった根本的な対応までには届いていない。これが西洋医学/現代医学の現状です。
1. アトピー患者さんを多く完治させている治療法
アトピー性皮膚炎は治る病気です。
冒頭でそうお伝えしましたが、はい、実際に まつもと漢方堂はアトピー性皮膚炎を完治させ、丈夫でキレイな皮膚を取り戻された方を10人以上、また500人以上の方の改善に立ち会ってきました。
これは、西洋医学/現代医学の「症状が出ないようにコントロールする」という治療とは目指しているゴールが異なります。治っていかれたみなさんは、もう皮膚科のお薬は必要ありません。とくに薬を使わなくても、皮膚に赤みも痒みも出ない身体になったのです。
ではそれはどんな方法だったのでしょうか。
この章ではいよいよ、まつもと漢方堂が取り組んでいる「中医学」の観点から見たアトピーという病気についてと、具体的な治し方についてお伝えしてきます。
・中医学から見たアトピーの原因と発症
中医学的には、アトピー性皮膚炎は「もともとの体質の弱点」があるところに、「老廃物が熱を持って皮膚へとあふれてくる」病気だと考えています。
弱点には「胃腸が弱くて老廃物が残りやすい」「自律神経が過敏で痒みが起こりやすい」「バリアの働きや皮膚の構造が脆弱」「ストレスの影響を受けやすく、メンタルから皮膚の症状が起こりやすい」「もともとの免疫状態がよくない」などの種類があります。弱点はひとりのひとにひとつとは限らず、2種類以上の弱点を同時に併せ持っているひともいます。
こうした弱点を持ったひとに、ストレス・過労・栄養過多などの負荷がかかると、体内で老廃物が発生します。この老廃物は体内に長く留まると次第に熱を帯び(湿熱)、アレルギーなど何らかの刺激で皮膚に炎症が起こると勢いよくそこからあふれ出します。平らだった皮膚がプツプツと盛り上がったり、プツプツが融合して腫れぼったくなるのはこのせいです。
熱を持った老廃物(湿熱)と、湿熱に伴って発生するその他の「熱」の要素の複合体がアトピー性皮膚炎の正体だと中医学では考えています。
・中医学から見たアトピーの症状
アトピー性皮膚炎の症状は、「急性期」と「慢性期」で現れ方が異なります。これを中医学的には、「邪気の盛んな時期」と「もともとの体質の弱点がメインで表れている時期」と理解しています。順に解説します。
「急性期」では、何らかの刺激によって炎症症状が現れます。皮膚に「プツプツ(丘疹)」「赤み(紅斑)」が見られ、強い痒みを伴います。症状が強いと部分が熱くなり(皮膚温の上昇)、自分でも熱さを感じます。プツプツが融合して腫れぼったくなる(浮腫)こともあり、痒みに掻き壊してしまうと黄色い汁(滲出液)が出ます。
平らだった皮膚にプツプツや腫れぼったいなどの「膨らみ」が起こり、引っ掻くと液がにじむ・・・そこには「水っぽい何か」が存在していますよね!
中医学ではこの「水っぽい何か」を「湿」のタイプの邪気(=病気の正体)と考えます。
「湿」はいろんな原因で発生しますが、胃腸の消化力が弱い、または自分の消化力以上に食べたり飲んだりしている、そんなときによく発生します。
また皮膚が赤くなっている部分は触ってみると熱く感じられます。プツプツも肌色のままではなく、赤く色がついていたり。こうした「赤」の色は「熱」のタイプの邪気の特徴です。引っ掻いて出る液は黄色く色がついていたりしますが、「熱」のせいで体液が煮詰められた状態だと考えています。
これら「湿」と「熱」が合体した「湿熱」の邪気、これがアトピー性皮膚炎の正体です。
先に述べた、湿気が強まり気温が上がりがちな梅雨どき以降、夏にアトピー性皮膚炎が悪化しやすい理由は、これです。「湿熱」の邪気が、環境の湿気と高温で勢いづけられてしまうのです。
「湿熱」は長く体内に存在すると、仲間(他の邪気)を増やします。アトピー性皮膚炎で見られる邪気はたくさんありますが代表的なところで、赤みが強いのは「血熱」、炎症が強くどんどん周囲へ炎症性物質をまき散らしてしまうのは「熱毒」と分類しています。
「慢性期」では、急性期のような激しい症状はありませんが、まだ皮膚にはうっすらと赤みが残り、カサカサと乾燥性の痒みが起こります。部分の皮膚はキメが荒く、細かいシワのよったような特有の肌状態(アトピックドライスキン)が残っています。
急性期からの痒みに掻き壊しが続くと、皮膚がゴワゴワと厚くなったり(苔癬化)、茶色~グレーに色が残ったり(色素沈着)することもあります。
「邪気」の勢いが弱まりアトピー性皮膚炎の炎症が鎮まってきた分、「もともとの体質の弱点」が目立ってきます。「ちょっと合わないものを食べるとすぐ湿疹が出る」なら胃腸の消化吸収力低下、「ショックなことに出会うと痒みが増す」なら自律神経系の不安定さ・・・などなど、本来の弱点ケアが必要な時期です。
・中医学から見たアトピーの悪化
「もともとの体質に弱点」があるところに、「何らかの刺激」が加わるとアトピー性皮膚炎は悪化します。アトピー性皮膚炎には波があると言われるゆえんです。
「何らかの刺激」とは「湿熱」を初めとするアトピー性皮膚炎を起こす「邪気」として人体に作用するものですが、ひとによっていろいろなものが刺激となります。代表的なものを4つ挙げます。
まず、アレルギー反応です。直接触れるもの(洗剤や化粧品など)や空中に飛んでいるもの(花粉やPM2.5など)による刺激が痒みや赤みを呼び、アトピー悪化につながります。
それから、先にも述べた夏の高温多湿です。梅雨どきや台風など、とくに湿気が強いときにプツプツや痒みが増す方、とても多いですね。
湿気は多いと悪化しますが、一方、乾燥でも悪化する方がいます。乾燥するとバリアの脆弱性に拍車がかかるため、刺激が皮膚内部へ侵入しやすくなりますし、乾燥によって痒みが増し「掻く」という物理刺激で悪化することもあります。
次に「食べもの」です。そのひとがアレルギー反応を起こすものはもちろんですが、それ以外に皮膚に炎症があるときに食べると悪化させがちだと分かっているものがあります。この「皮膚の炎症を悪化させがちな食べもの」を「発物」と呼んでおり、症状がある間、とくに急性期は避けた方が早く治ります。発物については別項で解説します。外食やファストフード、お菓子など炎症の起こりやすい食べものが続くと、さらに悪化しやすくなります。
このほか、ストレスや過労、睡眠不足、風邪などほかの「外邪(外界から侵入してきて病気を引き起こす原因)」もアトピー性皮膚炎を悪化させることがあります。
・中医学から見た「再発」
前項で述べたような悪化要因があると、その刺激でアレルギー反応が再燃し、炎症が強まります。炎症の勢いが強ければ、赤く腫れてプツプツ、ジュクジュク……といった「急性期」に戻ってしまうこともあります。
よくなったように見えても「慢性期」では皮膚の奥に微少な炎症が続いています。山火事は完全に消えきるまで、ちょっとの油断で火の手が上がりますね。アトピー性皮膚炎もまったくその通りです。完全に火が消えきるまで、炎症対策の手を緩めてはいけません。
・中医皮膚科の治療の目標
では、中医学ではどのようにアトピー性皮膚炎を改善するか。
個別にいろんなケースがありますが、大枠では以下の3段階で進めていきます。
1.「急性期」にはまず「湿熱」を中心とした「熱を取っていく
2.「慢性期」には大分弱くなった「熱」をさらに消していきつつ、「もともとの体質の弱点」の克服を図る
3.最終的には、再発しない丈夫な肌・身体を再生する
3の「丈夫な肌」は当然見た目も明るく、ハリやツヤがあって美しいです。1、2の段階で色素沈着やゴワゴワ(苔癬化)が残ってしまっている場合は、2の後半から3の段階でこれら炎症の痕跡も消していきます。
・中医皮膚科では何をするか<具体的な治療法>
わたしが学んだ中国の大学病院では、日本でもよく知られた漢方薬の煎じ薬だけでなく、アンプルや丸剤といった内服に加え、点滴・注射や外用も行われていました。
日本で点滴はできませんが、漢方薬の内服と、生薬エキスを溶かした液をカット綿に含ませて患部に数分載せておく「シップ」や漢方軟膏といった外用を併用します。内服(飲む)の漢方薬は、エキス剤と呼ばれる顆粒や錠剤になったものを使用します。一部は漢方「薬」ですが、中医学で皮膚症状に使われる漢方薬の一部は法律上「食品」に分類されていることもあります。いずれにしても、挽いて粉にしたり煎じたりといった手間はかかりませんので安心してください。
こうした方法を組み合わせ、前項で述べた1、2、3のステップそれぞれに必要なお手当を選択します。ステップに合っていない、またそのひとの身体に存在する「熱」の種類や「弱点」とぴったり合うように、ひとりひとり段階段階で、オーダーメイドに漢方薬を組み合わせて治療するのが中医学のやり方です。
また、先にお伝えした通り、アトピー性皮膚炎は「波」のある病気です。悪化の波がやってくるときには、何らかの「悪化要因」があります。なるべく早くそれを見つけ、避けられるものは避け、避けられないもの(季節など)があるときは他の悪化要因を極力避けてやり過ごします。こうした生活上の工夫を「養生」と呼び、漢方薬の内服や外用と同じように効果があります。
5. まとめ
以上、アトピー性皮膚炎とはどういう病気であるか、西洋医学/現代医学と中医学の考えをそれぞれ見てきました。
また、西洋医学/現代医学の治療法とそのゴール、中医学の治療法とそのゴールを解説しました。
症状のコントロールだけでなく、治ったあとの「丈夫でキレイな皮膚(あなた本来の皮膚)」を取り戻すには、中医学(中医皮膚科)の方法がとても有効です。
これは、中医学でこそ叶えられる「治った」状態です。今アトピー性皮膚炎で悩むみなさんには、ぜひこの方法で治していただきたい、そのためには、まずこの方法で治ることを知っていただきたいです。
中医学によるお手当を始められるとき、とくに事前準備は必要ありません。病院へ通ってお薬を使っている方は、そのまま使っていて構いません。中医学のお手当でアトピーが改善していく途中で、お薬は不要になりますので安心してください。
もちろん、いろいろな情報に触れるうちに、ステロイドを止めてしまった方も相談に見えます。いきなりお薬を止めると思わぬ悪化を見ることがありますが、こちらも中医学のお手当が有効です。
ここまでお読みになって、中医学によるお手当が自分にも効果があるかどうか知りたくなった方は、ぜひまつもと漢方堂の漢方相談にお越しください。あなたの「熱」の種類や段階、もともとの体質の弱点はどこか、それらを具体的にどのように改善していくか、気をつけるべき生活上のポイント、今後の見通しなど、中医学の分析に沿って分かりやすい言葉でお伝えいたします。実際に漢方薬でのお手当を希望される場合は、すぐその場で必要なお手当をお渡しいたします。
丈夫でキレイなお肌を、あなたも取り戻してくださいね。
参考文献
*1:アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021
https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/guideline/ADGL2021.pdf
*2:秋山 真志,アトピー性皮膚炎におけるフィラグリンの異常,2008年,臨床皮膚科62巻5号
*3:吉田 和恵,乳児脂漏性皮膚炎,2022年,小児内科 54巻8号
*4清水宏,新しい皮膚科学第2版,株式会社中山書店,2011年,p111